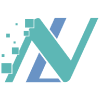お知らせ
福岡障害者戦力化会議にて講演させていただきました。
2025.03.21障害者雇用の安定と訪問看護の可能性
〜福岡障害者戦力化会議での講演より〜
令和7年3月21日、福岡県内の大手企業様が一堂に会する「福岡障害者戦力化会議」にて、私は「訪問看護の役割と障害者雇用支援への可能性」について講演させていただきました。今回の会議には、TRIAL様、ASKUL様、NTT西日本様、九電グループ様、清水建設様、さくら病院様など、福岡を代表する企業の皆様がご参加され、障害者の就労支援に対する熱意と実践を肌で感じることができました。
私たちが運営する訪問看護ステーションは、精神疾患および発達障害に特化した看護を提供しています。特に就労中または就労を目指す障害のある方々に対し、医療と福祉の視点からサポートを行っており、その中で見えてきた課題や解決策を、今回の会議でお伝えしました。

訪問看護とは何か
訪問看護とは、医師の指示のもと、看護師や精神保健福祉士がご利用者様のご自宅に伺い、療養生活をサポートするサービスです。私たちのステーションでは、精神疾患や発達障害を持つ方々の「日常の安定」と「社会参加」を目的とした支援に力を入れています。主な支援内容は以下の通りです:
-
服薬の管理と内服の動機づけ
-
感情のコントロール支援
-
生活リズムの調整
-
職場でのストレスへの対処法の習得
-
対人関係やコミュニケーションのサポート
訪問看護の最大の特徴は、個別性の高さと、医療専門職による継続的な関わりが可能である点です。これにより、急性期の再発防止や、離職のリスク軽減、就労の継続支援が可能になります。
企業様から伺う障害者雇用における課題
会議の中で多くの企業様より、「採用したものの継続的に働いてもらうことが難しい」「メンタル不調や急な欠勤の対応に悩んでいる」といった声がありました。また、発達障害特有のコミュニケーションの難しさや、職場での配慮の方法がわからないという課題も挙げられていました。
このような悩みは、障害の特性理解と個別支援の工夫によって、十分に軽減することが可能です。たとえば、「指示が曖昧だと理解できない」「感覚過敏により職場の音や光にストレスを感じる」など、特性に合わせた業務調整や説明方法の工夫が必要です。
訪問看護による実際のサポート事例
ある発達障害の方は、大手企業に障害者雇用で就職したものの、欠勤が増え勤怠が不安定になりました。企業側では、どのように対応すればよいかわからず困っていましたが、訪問看護で介入を開始し、以下のような支援を行いました。
-
欠勤が増えて来た、勤怠が安定しない状況や心境の把握
-
就労時におけるストレス状況の把握と対策方法
-
3週間ほどの休職と再開時に企業訪問し上司とのミーティングに同席し、今後の業務内容の確認
-
医師との連携で就労状況の共有
このような介入を経て、欠勤は大幅に減り、現在では就労時間を伸ばしながら安定して勤務を継続されています。企業からも「専門職が間に入ってくれることで安心感がある」と好評をいただいています。

訪問看護を企業に導入する方法
精神科訪問看護は医療保険を用いて導入することが可能です。就労中の方の場合、「自立支援医療(精神通院医療)」の活用が最も一般的です。
導入の流れとしては以下の通りです:
-
本人またはご家族、企業担当者より訪問看護へ相談
-
精神科主治医から訪問看護指示書の発行
-
ご利用者様との契約、看護計画の作成
-
週1〜2回程度の訪問開始(状況により柔軟に対応)
企業が直接契約するのではなく、あくまで「本人の生活支援・就労支援」の一環として行われるため、企業側の負担はありません。また、必要に応じて企業との連携・ミーティングにも同行可能です。
今後の展望と皆様へのお願い
障害者雇用の現場において、「安定して働き続けられる仕組み」をつくることは大きな社会的課題です。訪問看護はその一助となる可能性を持つ支援策であり、もっと多くの企業様に知っていただきたいと感じています。
企業様には、まずは「つながること」から始めていただきたいと思っています。どんな些細なことでも、現場での困りごとや悩みを共有していただければ、私たち医療専門職ができる支援を一緒に考えることができます。
最後に、「障害のある方が自分らしく働ける社会」は、決して理想論ではありません。福岡の企業の力、そして地域の専門職との連携によって、確実に実現できる未来です。
ご希望に応じて、このコラムの内容をパンフレット化、スライド資料化、あるいは別メディアへの投稿用に再編集することも可能です。必要でしたらお申し付けください!